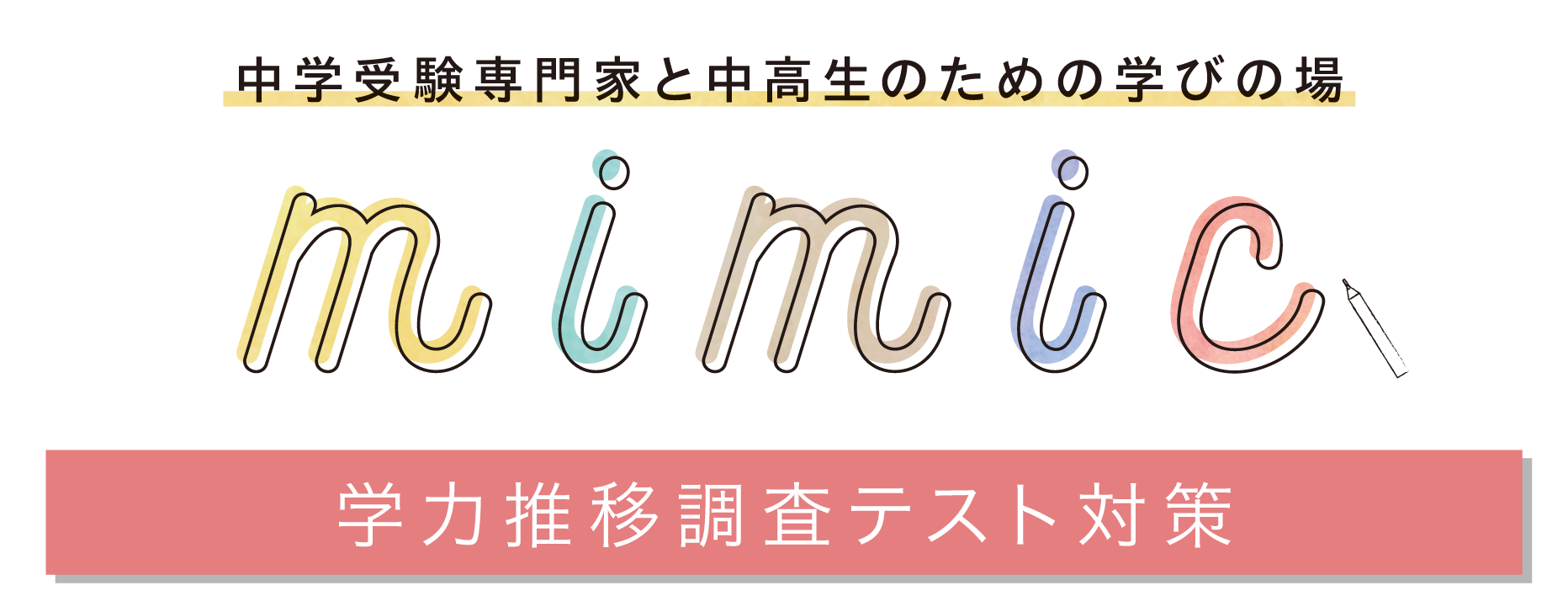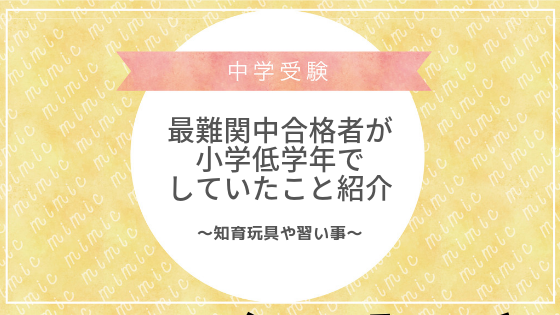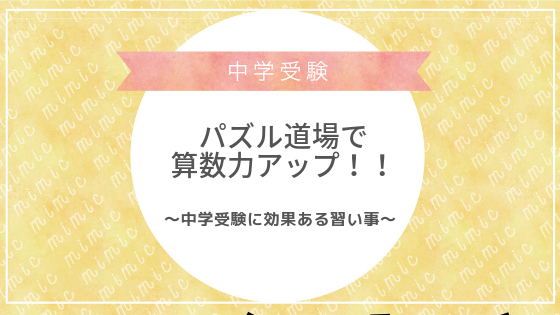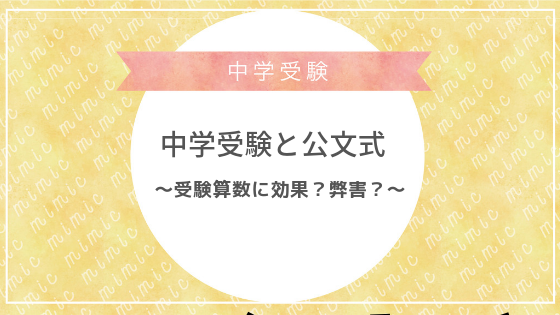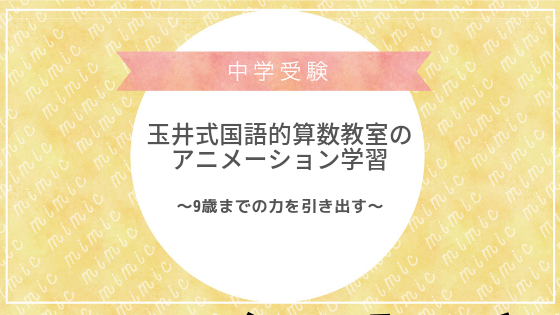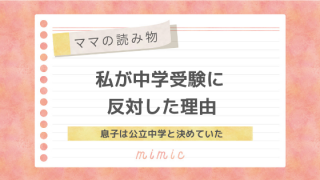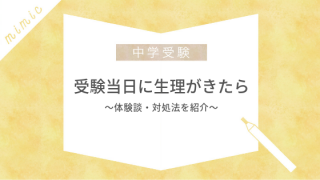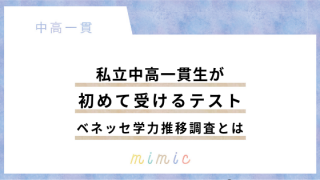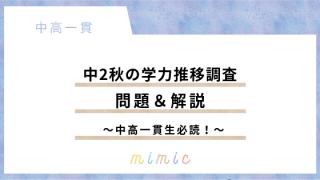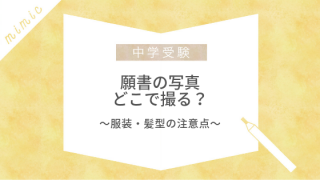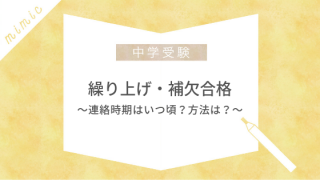こんにちは、mimiです。
今日は寒いです。
まだ、一部終わらない中学がある期末テスト勉強。
最後まで頑張ってほしいです。
さて、今日は「あの中学に合格するためにしてきた事って何?」と、よく聞かれる質問についてです。
ちょっとタイトルが生意気で申し訳ないです。
実際、うちの息子がしてきた遊びや習い事について書きます。
・灘/東大寺学園中に合格するための幼児教育は?
・受験勉強の息抜きは?
・これはやっておいて良かったということは?
昨日の記事昨日の記事に書いたように、中学受験に反対しているような親でしたから、語る資格があるもんか悩むところです。
でも、本当によく聞かれる内容なんです。
中でも一番良く聞かれるこの質問に答えようと思います。
きょうだいみんな灘ママさんのような有益情報はないと思います。
こんな母親もいるのか、程度に参考にしてください。
見たいところをクリック
灘/東大寺学園中に合格するための幼児教育は?

最初に言うと幼児教育的なことは、何にもしていません。
保育園に2歳と0歳から通園していたんで、就学前はほとんど保育園で育っているんです。
「のびのび自由に」がモットーの保育園でしたから、文字なんかは入学前に大急ぎで教えたぐらいです。
習い事は「学研」をしていました。
それも教材より教室にあるジグソーパズルやお絵描きメインでなかなか教材をしないっていうね。
だから、パズルとお絵描きは誰よりもしている!!!
のは、間違いありません。
それぐらい大好きでした。
休日は新聞紙をリビングに一面敷いて、粘土遊び・お絵描き・ピクニックもどき(朝から作ったお弁当をそこで食べる謎の遊び?)を毎週していました。
美術系なのかな?と思うぐらい、絵を描いて、自分たちで最終パズルを作ってました。
2歳差兄弟なんで、このあたり共同作業が多かったです。
ギリギリ家庭学習カウントしてもいいかなという息子たちが大好きだったおもちゃやゲームが以下の品々です。
【就学前編】
小学校入学までによく遊んだ中で、なんだか勉強に役立ったかもしれないという物を紹介します。
プラステン
なんでしょう、めちゃくちゃお気に入りのおもちゃでした。
長男から次男、次男から三男へと引き継がれ、今は教室のインテリアと化しています。
数の概念の第一歩のような遊び方をしていたはずです(覚えていない)
最初は積み木のような遊び方、色合わせとか、子どもが勝手に色んな使い方をして遊んでました(たぶん)
この玩具の本来の使い方を息子たちもわたしもあんまりわかってないかもしれません。
でも、小学校に入ってから「プラステンしてたから」と言う言葉をよく聞きました。
いま、「何に役立ったの?」と聞いても「たぶん算数」というだけでもう忘れてしまってます(すみません)
レゴブロック
言わずと知れた「レゴ」です。
踏んではキレてましたが、めちゃくちゃ創作に強くなりました。
決まった形より自由に作る方が好きな子どもでした。
くもんのジグソーパズル
Step1からあり、最初は大きなパズルが4枚とかです。
3歳頃から遊んでた気がします。
全STEP持ってました。
このパズルはけっこう本気でおススメです。
ビックリするほど集中します。
パズル好きな子どもなら静かに何時間でもやり続けます。
乗り物や恐竜など、子どもの好みに合わせて選べます。
ブロックス
5歳ごろから受験前までしてましたし、未だに三男が「やりたい!」と言うと、mimic内にいる子ども皆が楽しめる対戦ゲームです。
スマブラやスプラも大好きなわたし、我が子ですが、このブロックスも大好きです。
これは考える力がつきます。
そして大人も手抜きせず子どもと同じ目線になり遊べます。
家族みんなが楽しめるんでコスパも最高です。
【小学生編】
小学校に入学してからよく遊んでいたものです。
ダントツで3DSですが、電子ゲームした分そうじゃないことをする、との決まりを作ってたので全ての玩具で、満遍なく遊んでいた気がします。
3DS
ええ・・ゲーム・・?と思わないでください。
長男が入学して初めて手にしたんですが、ポケモンシルバーを一緒に楽しみました。
親子のコミュニケーションに使ってました。
平成生まれの子どもを語るのに、ゲームを外すのは無理があると思うんです。
個人的にロールプレイングゲームは悪くない、と思いました。
物理・原子 原子モデルカードゲーム
これは、カードゲームの中でもめちゃくちゃお気に入りでした。
未だにmimicで使うんで1000円でお釣りがくる、このカードゲームもコスパ最高です。
化学記号を習ったとき「絵、あのカードのゲームって勉強やったん?」て言ってました。
勉強を遊びにするというのは効率良いですね。
何も考えず適当にポチった自分を褒めたくなりました。
オセロ
今昔変わらない遊びの代表と思っています。
ルール説明もいらないので、いきなり遊べて今も盛り上がります。
スマホゲームやパソコンゲーム、DSやvitaも面白いし、古典的ゲームも絶対面白い。
これは仕方ないと思います。
顕微鏡
なんでも見てました(笑)
顕微鏡使うことが授業であるから、使い方や手順を覚える手間が省けました。
百聞は一見に如かず、に役立ち、好奇心を育ててくれたと思います。
受験勉強の息抜きは?
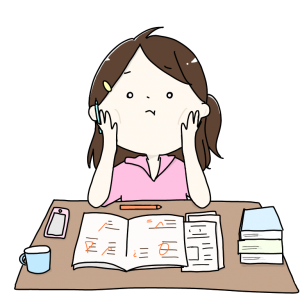
6年生から電子ゲームを封印したので、息抜きはブロックスと物理・原子 原子モデルカードゲームが多かった気がします。
国語嫌いでどうしよもなかったんで、ちょっとでもマシになるよう気休めに就寝前に読んでもらっていたのはこちら。
もう、勉強に疲れたから寝る、となったら読むように言いました。
これぐらいですね、わたしが強制したことは。
色んな人物がいる、と視野を広げてほしかったのと、1ページぐらい頑張って読め、という気持ちからであまり受験に関係ないかもしれないです。
これはやっておいて良かったということは?

上に書いたすべてと習い事ですね。
習い事は、どれもこれも「やって良かった」しかないです。
【中学受験に効果的】玉井式国語的算数教室で9歳までに学んだ効果と【中学受験】パズル道場で算数力up!は具体的に記事でどんな良さがあるか書いてあるので参考にしてください。
これ以外で息子たちがしていた習い事を紹介します。
・スイミング
・ダンス
・バスケットボール
・テニス
・英会話
ほとんど運動です。
2人とも気管支が弱かったんで、風邪なのか喘息なのかわからない咳き込みをしてたんです。それを改善するために全て始めました。
受験をそもそもさせる気がなかったんで、なんか運動したら?ってことで広く浅く色々していました。
長男のスイミング、次男のバスケットボールが長く続きましたね。
英会話は小学1年生から2年生まで1年だけ習いました。
やってみて全然身につかなかったんで(笑)やめました。
やり時があるのかな?って思って。
結局、受験勉強で小学校の間に英語に触れることはありませんでした。
続けられるなら、間違いなく長男はスイミング、次男はダンスかバスケットボールと言うと思います。
わたしは、本人がやる気のないことをさせるのが嫌いなんで習い事に関しては本人が食いついたものしかさせていません。
まとめ
ビックリするほど何もしてなくて、反省してます。
それで合格できるの?!とムカつく方もいるかもしれません。
考えて考えた結果。
わたしは常々、勉強できそうな時間、だけは自発的に作り、意識してきました。
そこぐらいしか思い浮かびません。
あとは、「いいな」と思ったゲームなんかが、役立ってくれていたことです。
おもちゃやゲームと侮(あなど)れません。
こんなに楽しいものを規制するって難しいんだろうな、と思います。
だから、小学校1年生までは絶対電子的なゲームには触れさせていませんでした(当たり前なんでしょうか)
就学前は就学前の、小学校低学年には低学年の時期に適した遊び・やるべきことがあります。
そこをすっ飛ばして幼児教育するのは自分の肌に合いませんでした。
時期にあったことをしていたら、幼児教育する時間なんか微塵もありませんでした。
よく遊び、よく学ぶって難しいと思いましたもん。
遊んでたら寝る時間が来るし。
ということで、家庭の協力やお母さん、お父さんしいては家族のバックアップ。
何よりも本人の努力と少々の元々あるだろうポテンシャルによって進度は変わるのではないだろうか、と夫婦で結論付けました。
中高がどうでも、最終的には仕事をしてくれないとお話にならないので、勤労の義務を果たす大人になってくれたらそれでいいかな、という無欲さや過剰な期待をしないことも本人たち的には気楽だったようです。
存分に勉強する時間と環境は大事かもしれない、とは思います。